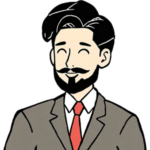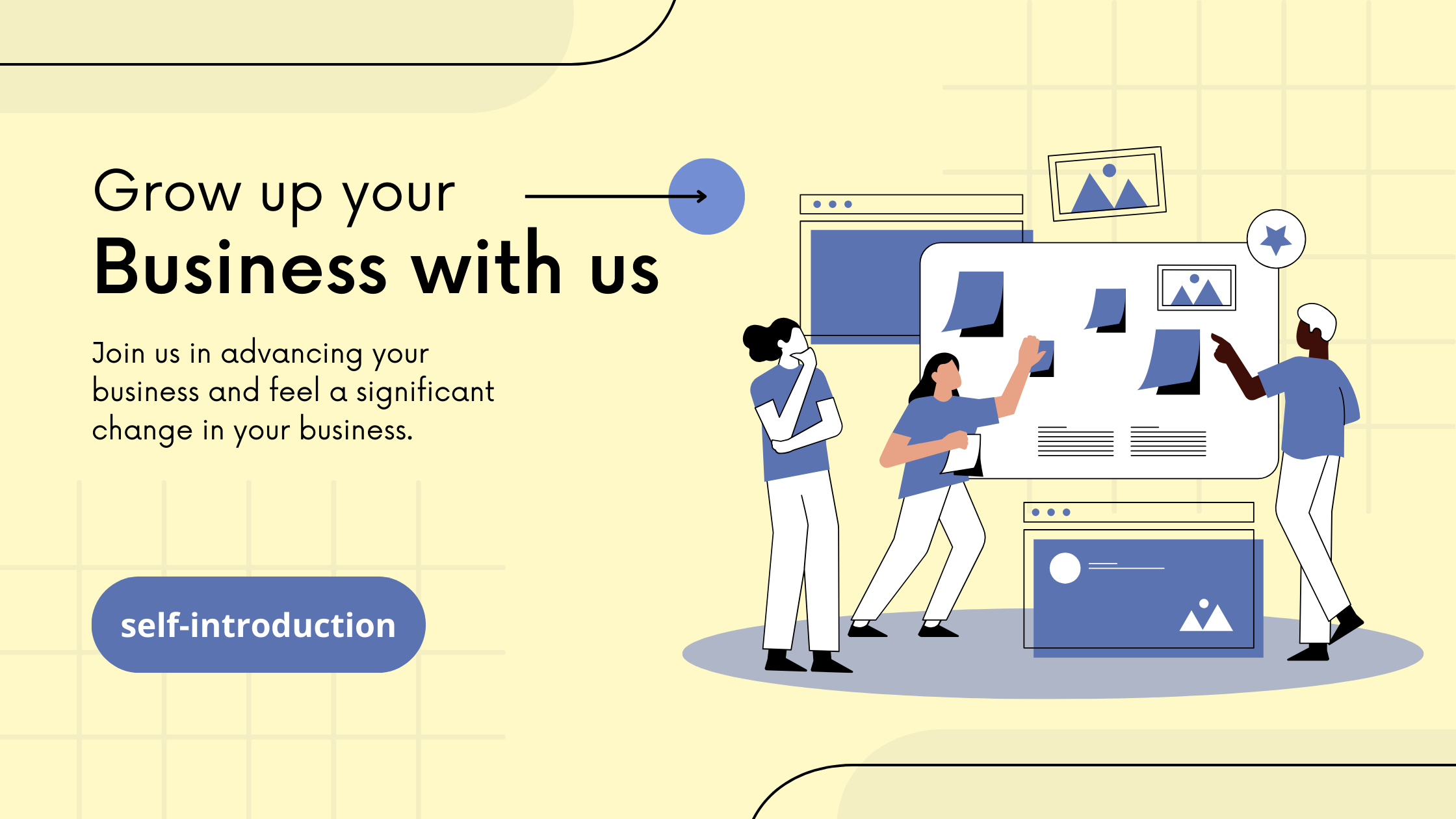【転職の歴史】日本における転職文化の始まりとその変化とは?
「転職はキャリアアップの手段」「1社に縛られない働き方が大事」
今でこそ当たり前になったそんな価値観。でも少し前までは、転職=根性なし・脱落者と見なされていた時代もありました。
この記事では、日本の転職の歴史を時代ごとの流れで解説しつつ、当時の象徴的な転職事例を交えて、「なぜ転職は一般化したのか?」を深掘りしていきます。
明治時代:職業選択の自由が生まれた時代
明治維新によって身分制度が廃止され、士農工商の垣根がなくなったことで、日本でも「職業選択の自由」が生まれました。
とはいえ、転職はまだ社会的に珍しく、仕事を変えること=信用を失う行動と見られる傾向が強かったです。
▶ 象徴的な事例:
福沢諭吉(学者→新聞創設→教育者)
封建的な身分から抜け、自由な思想を広めるために複数の職を経てキャリアを築いた先駆者の一人。
昭和初期〜戦後:終身雇用の定着と転職への偏見
第二次世界大戦後の復興により、企業が安定成長を遂げていく中で、「終身雇用・年功序列」制度が定着しました。
転職する人は極めて少なく、社会的にも「辛抱が足りない」「落ちこぼれ」など否定的な評価が根強かった時代です。
▶ 象徴的な事例:
石橋正二郎(ブリヂストン創業者)
父の足袋製造業を継ぎながらも、「タイヤこそこれからの時代」と見抜き、事業転換。
職業的な転身と企業転換の先駆者とも言えます。
高度経済成長期:転職は一部の人だけの選択肢
1950〜70年代の高度経済成長期。企業は右肩上がりで新卒採用に注力し、転職市場はほぼ存在しませんでした。
「一社に骨を埋める」ことが正義であり、転職=キャリアダウンというイメージが強固に。
▶ 象徴的な事例:
盛田昭夫(ソニー創業者)
東京通信工業(のちのソニー)を創業した際は、大企業志向の時代に“独立”すること自体が異端。
いわば「終身雇用社会に風穴を開けた人物」。
バブル崩壊後:リストラと共に転職が表面化
1990年代、バブル崩壊により大企業でも倒産・リストラが相次ぎました。
「会社にいれば一生安泰」という神話が崩れ、やむを得ず転職する人が急増します。
▶ 象徴的な事例:
村上世彰(投資家・元官僚)
大蔵省を辞めて村上ファンドを設立。
安定志向の公務員→民間起業家へという異例の転職が大きな話題に。
2000年代:転職が“戦略”になる時代へ
インターネットの普及により、転職サイトやエージェントが一般化。
企業も中途採用に積極的になり、転職がキャリア形成の選択肢のひとつとして定着し始めます。
▶ 象徴的な事例:
堀江貴文(ホリエモン)
東京大学在学中に起業し、ライブドアで急成長。
学生→起業→IT企業の経営者へと転身。
“自分で道を切り拓く”という新しい働き方の象徴となる。
2010年代以降:転職は“当たり前”の選択肢に
副業解禁、働き方改革、リモートワークの普及…。
仕事のスタイルが多様化し、転職は特別なことではなく、むしろ“自分らしく働くための手段”に。
▶ 象徴的な事例:
田端信太郎(元LINE・ZOZO執行役員)
リクルート、ライブドア、LINE、ZOZO…と名だたる企業を渡り歩きながら、
**“企業に属しながら自分のブランドを確立する”**キャリアモデルを体現。
✔ まとめ:転職の価値観は、時代とともに大きく変わった
| 時代 | 転職のイメージ | 代表的人物例 |
|---|---|---|
| 明治 | 職業選択が可能に | 福沢諭吉 |
| 昭和 | 転職=忍耐不足 | 石橋正二郎 |
| 高度成長期 | 転職=キャリアダウン | 盛田昭夫 |
| バブル崩壊後 | リストラが転職を促進 | 村上世彰 |
| 2000年代 | 転職=キャリア戦略 | 堀江貴文 |
| 2010年代〜 | 自由な働き方の手段 | 田端信太郎 |
💬 最後に:あなたにとっての「意味ある転職」とは?
転職の意味は、時代や社会によって大きく変化してきました。
でも大切なのは、「どこで働くか」ではなく「どう生きたいか」。
転職は、人生の方向を自分で選ぶための手段の一つ。
“逃げ”ではなく、“選択”としての転職を、ぜひ自分らしく考えてみてください。
✍️この記事が参考になったら、SNSシェアやコメントで感想もらえると励みになります!